0. はじめに
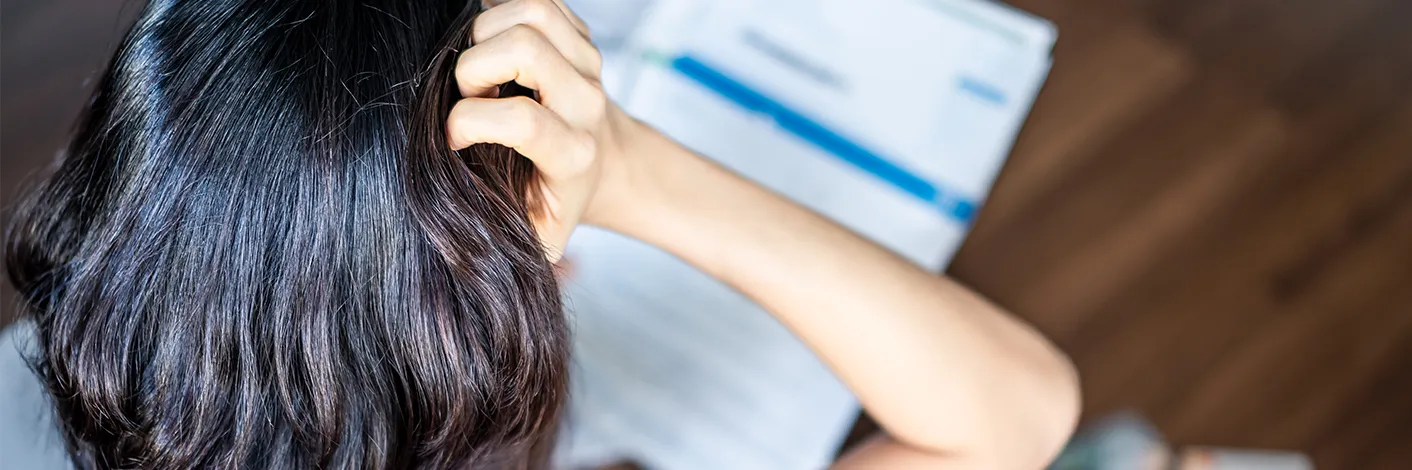
借金返済に追われる生活に疲れてしまい、借金を少しでも減らしたいと考える人もいるでしょう。
実は、個人再生という手続きを利用すれば、自宅や自動車などの高価な財産を手放すことなく、借金を大幅に減額することが可能です。
しかし、個人再生には煩雑な手続きが多いため、正確に対応していかないと失敗に終わってしまいます。
このコラムでは、個人再生の手続きに失敗してしまうケースや、弁護士に手続きを依頼するメリットなどについて詳しく解説します。高額な借金の返済に困り、個人再生を検討中の方はぜひお読みください。
1. 個人再生とは
個人再生は裁判所に申立てを行い、再生計画の認可を受けることで、借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)の分割払いで返済していく手続きです。
個人再生は、自己破産のように借金の返済が免除されませんが、自宅や自動車などの高価な財産を残すことができます。
また、任意整理とは異なりすべての借金が手続きの対象となりますが、任意整理よりも借金を大きく減額し、生活の立て直しを図ることが期待できます。
2. 個人再生の条件

個人再生を成功させるためには、次のような条件を満たす必要があります。
条件を満たしていないと申立てが却下・棄却されてしまうことがあるので注意しましょう。
- 再生計画に沿って返済ができる程度の安定した収入がある
- 住宅ローンを除いた借金総額が5,000万円以下である
手続きをスムーズに進めるためにも、個人再生の条件について弁護士に相談することをおすすめします。
3. どれぐらいの人が個人再生に成功しているのか
裁判所の司法統計(2022年版)によると、2022年に個人再生の手続きが終わった総数は10,351件で、このうち認められた(成功した)件数は9,535件でした。
成功率は約92.1%で高い割合となっていますが、この中には弁護士が申立代理人となっているものを多数含んでいますし、約8%の方が失敗に終わっているため、「個人再生は簡単」と考えてはいけません。
4. 個人再生が失敗するケース
個人再生を申立てたからといって必ず認められるわけではなく、適切に手続きを進めないと、失敗に終わることもありえます。
失敗すると借金の大幅な減額が認められないだけでなく、減額自体が認められない可能性もあり、手続きにかかった時間や費用が無駄になってしまいます。
確実に個人再生を成功させるためにも、手続きが失敗してしまうケースについて、理解しておきましょう。
- 特定の債権者に優先して借金を返済する(偏頗弁済)
- 再生計画案の提出期限を守らない
- 虚偽の申告をする
- 履行テストを怠る
- 新たな借入れをする
- 債権者から反対された
- 返済を滞納する
4-1. 特定の債権者に優先して借金を返済する(偏頗弁済)
複数の債権者がいる場合、一部の債権者に対して優先的に返済をしてはいけません。たとえば、自動車が引き揚げられるのを防ぐため、自動車ローンを組んでいる金融機関に対して優先的に返済するような行為です。
このような行為を「偏頗弁済(へんぱべんさい)」と呼び、民法の原則である「債権者平等の原則」に反します。
なお、友人や家族から借金をしている場合、優先的に返したいと考えるかもしれませんが、やはり偏頗弁済となる可能性が高いです。
4-2. 再生計画案の提出期限を守らない
個人再生を成功させるには、裁判所に再生計画案を提出して認めてもらう必要があります。再生計画案とは、減額後の借金をどのように返済していくかについて、説明する書類です。
再生計画案は、裁判所が定めた期限日までに提出しなければなりません。提出が1日でも遅れると手続きは廃止となり、失敗に終わってしまいます。
4-3. 虚偽の申告をする
個人再生を申立てる際、借入先や財産、収入額などを裁判所に申告します。申告内容に虚偽や不備があることが判明した場合、申立てが認められない可能性があります。
また、財産を隠蔽しようとしたなど、虚偽の内容が悪質と判断された場合は詐欺再生罪に問われることがあります(民事再生法第255条)。
4-4. 履行テストを怠る
個人再生の手続中、再生計画案の内容通りに返済していくことができるかを確かめるため、実際に返済を行う「履行テスト」が実施されます。履行テストできちんと返済できなければ、再生計画が認められず、手続きが失敗してしまう可能性があります。
4-5. 新たな借入れをする
手続きが始まってから新たな借入れをした場合も、個人再生が認められないでしょう。また、返済する意思がないのに借入れをしたとみなされ、詐欺罪(刑法第246条)に問われる可能性もあります。
4-6. 債権者から反対された
個人再生の手続きによっては、再生計画案の内容について債権者に賛否を尋ねる書面決議が行われます。債権者から一定数の反対を受けると、手続きが失敗となってしまいます。
4-7. 返済を滞納する
個人再生が認められた後は、再生計画に従ってきちんと返済していかなければなりません。滞納すると再生計画案の認可決定が取り消されて借金の減額がなかったものとなり、借金が元通りになる可能性があります。
計画通りの返済が難しい場合は、再生計画の変更を申立てて返済期間を延長してもらう、自己破産を申立てるといった方法で対応することが重要です。
5. 個人再生が認められないときの対処法
個人再生が認められなかった場合は、借金の金額は申立ての前と同じままです。
さらに、手続き中に利息や遅延損害金が加算されたことで、借金が膨らんでいる可能性があります。
個人再生に失敗した場合は、改めて申立てを行うことが可能です。しかし、状況が改善していなければ、また失敗となる可能性が高いため、転職して安定した収入を確保するなど、何らかの対応が必要です。
収入の確保などの対応が難しい場合、自己破産など別の債務整理を検討するようにしましょう。
6. 個人再生の手続きは弁護士に依頼

弁護士に個人再生の手続きを依頼することには多くのメリットがあり、個人再生を成功させるカギとなります。
- 借金の督促や取立てが止まる
- 煩雑な手続きを任せて失敗を防げる
- より最適な解決策を提案してくれる
6-1. 催促や取立てが止まる
個人再生などの債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は債権者に対し、債務者の代理人になったことを伝える「受任通知」を送付します。
受任通知を受け取った金融機関などの貸金業者(債権者)は、あなた(債務者)に対して直接取り立てることができなくなります。
弁護士に依頼すれば、債権者からの督促に怯えることなく、落ち着いた状況で個人再生の手続きを進められるようになります。
6-2. 煩雑な手続きを任せて失敗を防げる
個人再生は、数多くの書類を集めたり、作成したりするなど、煩雑な手続きを進めなければなりません。虚偽の申告をするつもりがなかったとしても、書類に不備があれば個人再生が認められない可能性もあります。
また、裁判所とのやり取りや、債権者の決議など、さまざまな手続きを適切に進める必要があります。弁護士に依頼すれば手続きを任せられるため、手続きにかかる手間を省けるだけでなく、失敗する可能性を大幅に減らすことができるのです。
6-3. より最適な解決策を提案してくれる
個人再生を希望していても、借金の残額や収入、財産によっては、任意整理や自己破産など、ほかの手続きを選択した方がよいケースもあります。
どの債務整理の手続きを選択するべきかについては、専門的な知識が求められるため、借金問題に詳しい弁護士に相談することが重要です。
また、個人再生の手続きには、大きく分けて「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
小規模個人再生は、給与所得者等再生に比べて手続きが簡単で、返済額が低額になるケースが多いですが、債権者の書面決議で一定数の賛成を得なければなりません。
一方、給与所得者等再生は、小規模個人再生より手続きが複雑で、返済額が高額になりやすいですが、債権者の決議が不要というメリットがあります。
個人再生を行う場合も、それぞれのメリットデメリットを理解したうえで、手続きを選択することが重要なので、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、債務整理に関する弁護士への相談を無料としております。借金問題の解決実績が豊富な弁護士が多数在籍しておりますので、安心してお任せください。


