- 0. はじめに
- 1. 自己破産すると現在の賃貸住宅から退去しなければならない?
- 2. 自己破産後に賃貸住宅を追い出されるケース
- 2-1. 家賃を滞納している
- 2-2. 収入に対して家賃が高すぎる
- 2-3. 保証会社の更新審査に通過できなかった
- 3. 自己破産すると新たに賃貸を借りられないって本当?
- 3-1. 賃貸物件の審査のしくみ
- 3-2. 入居審査では現在の収入・資産が重視される
- 3-3. 信販系保証会社は利用できない可能性大
- 3-4. 独立系保証会社は利用できる見込みが大きい
- 4. 自己破産後の入居審査に通らない場合の対応方法
- 4-1. 独立系保証会社を選ぶ
- 4-2. 連帯保証人をつける
- 4-3. 同居人の名義で申し込む
- 4-4. 公営住宅やUR賃貸を選ぶ
- 5. 自己破産が賃貸借契約の連帯保証人に与える影響
- 5-1. 自己破産すると連帯保証人が請求を受けることがある
- 5-2. 連帯保証人への影響を最小限に抑える方法
- 6. 自己破産後の生活の不安は専門家に相談を
0. はじめに
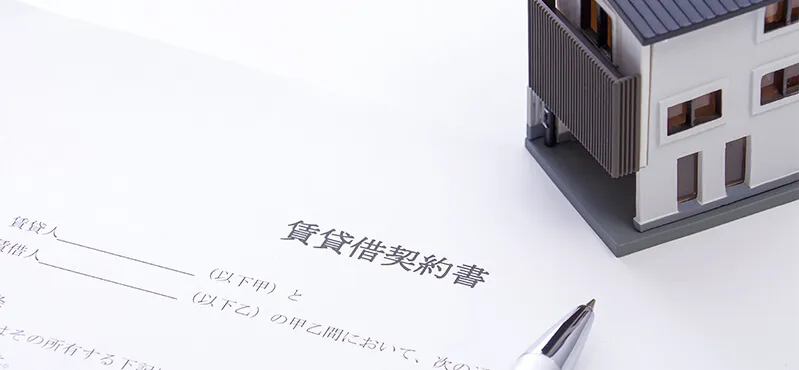
自己破産したことを理由に、今住んでいる賃貸住宅を追い出されることは、基本的にはありません。
ただし、家賃滞納がある場合や、保証会社の審査に通過できなかった場合は例外です。また、破産手続き後に新しく賃貸住宅を借りる際も、破産によって事故情報が登録されたことが原因で、入居審査に通らない可能性がゼロではありません。
このコラムでは、自己破産による賃貸借契約への影響について、借金問題に詳しい弁護士が解説します。破産後の住まいに不安をお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。
1. 自己破産すると現在の賃貸住宅から退去しなければならない?
自己破産しても、今住んでいる賃貸住宅の退去を求められることは原則としてありません。自己破産は高価な財産を処分する必要がありますが、その効果は賃貸借契約には及ばず、自己破産したことを理由とする契約解除も通常は考えられません。
つまり、家賃を滞りなく支払っている限り、自己破産をしても賃貸物件の契約は継続できるのが原則です。滞納などのトラブルによる債務がなければ、大家や管理会社が破産手続きに参加することはなく、破産の事実を知られることすら考えにくいでしょう。
仮に破産したことが大家などに伝わったとしても、これを理由に退去を求められることはありません。
法律上、大家から退去を求めるにあたっては、滞納そのほかの契約違反などといった「正当な事由」が必要となるためです。入居者の破産という事実のみでは、賃貸借契約の解除と退去を求めるための正当な事由にはあたりません(最高裁昭和43年11月21日判決)。
2. 自己破産後に賃貸住宅を追い出されるケース
ただし、必ずしも「自己破産後も今の賃貸物件に住み続けられる」とは断言できないため、注意しましょう。
たとえば、次のようなケースに当てはまる場合、自己破産することによって居住中の賃貸住宅から退去を迫られる可能性はゼロではありません。
- 家賃を滞納している
- 収入に対して家賃が高すぎる
- 保証会社の更新審査に通過できなかった
2-1. 家賃を滞納している
自己破産後に賃貸住宅の退去を求められる理由としてもっとも多いのは、家賃の滞納です。仮に破産手続きを開始しなかったとしても、過去の事例によれば、一般的な目安として滞納が3か月以上続くと賃貸借契約を解除できる正当な事由になるとされます。
家賃を滞納している場合、賃貸住宅の入居者について破産手続きが進行すると、大家が債権者として手続きに参加することができます。なお、手続きが終わるまで裁判所や破産管財人を通さずに家賃の支払いを直接行うことはできないため、結果的に長期間の滞納扱いとなり、退去を求められてしまいます。
また、賃貸住宅から追い出されないようにするため、滞納している家賃だけを支払うと、破産による借金返済の義務の免除(免責)が認められない可能性があります。特定の債権者にだけ返済する行為は偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれ、破産法により免責不許可事由として扱われるためです(破産法第252条1項3号)。
自己破産を行う必要があるときは、家賃など必要最低限の費用を支払える状況を確保してから手続きに踏み切ることをおすすめします。
もし、家賃の支払いに不安がある場合は、生活保護を利用する選択肢もあります。生活保護を受給すれば、自治体から家賃補助が出るため、経済的に安定しやすくなります。
自治体の福祉担当窓口に相談し、制度の利用について検討するとよいでしょう。
2-2. 収入に対して家賃が高すぎる
収入に対して家賃が高すぎる場合、自己破産の手続きの中で賃貸借契約を解除しなければならなくなる可能性があります。家賃の目安は一般に「手取り収入の3分の1以下」とされていますが、ほかの支出も考慮して無理のない範囲に抑えるべきです。
自己破産は借金の返済が難しくなった人の生活を立て直すための手続きです。しかし、家賃が高額な賃貸住宅に住んでいる場合、免責が認められても生活を立て直せないかもしれません。
裁判所から選任される破産管財人は、破産者の生活の立て直しのために必要な権限を持っており、破産者の賃貸借契約に関する決定もできます。そのため、家賃が高すぎると管財人から判断された場合、破産管財人から賃貸借契約を解除されてしまうことがあるのです。
2-3. 保証会社の更新審査に通過できなかった
自己破産すると、賃貸物件の保証会社の更新審査に通りにくくなってしまうかもしれません。更新審査に通過できない場合、すぐに追い出されないとしても、契約を更新できず結果的に退去が必要となる可能性があります。
特に、「信販系保証会社」に該当する会社が保証会社となっている場合は注意しなければなりません。
賃貸物件の契約では、大家との契約にあたって連帯保証人もしくは保証会社(あるいはその両方)をつけるのが普通です。保証会社には複数の種類があり、なかでも信販系保証会社は、更新の審査時に個人信用情報機関を通じてこれまでの融資の記録を参照します。
こうした保証会社による更新審査は、借金を返済できず自己破産した履歴(事故情報)がある、いわゆる「ブラックリスト」に載った状態だと、著しく不利になります。
3. 自己破産すると新たに賃貸を借りられないって本当?
「自己破産すると新しく賃貸物件を借りることができない」と聞いたことがある人もいるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。入居審査のしくみや保証会社の種類を理解し、物件選びの段階から注意することで、新しく家を借りることはできます。
自己破産の手続き後に引っ越す予定がある人は、ここで紹介するポイントを押さえましょう。
3-1. 賃貸物件の審査のしくみ
借家の賃貸借契約を締結する際の審査には、「入居審査」と「保証審査」の2段階があります。入居審査は大家が行い、保証審査は大家が指定した保証会社が行います。
それぞれ審査目的が異なり、自己破産後の申し込みで注意したいのは「保証審査」のほうです。
- 入居審査とは
家賃滞納や近隣トラブルを起こさない人物か確認するための審査
- 保証審査とは
家賃の支払いについて保証するため、支払い能力を確認するための審査
なお、保証審査が行われるのは、家賃支払いが難しくなったときに代わりに返済を行う当事者として、契約上「保証会社」が入る場合に限られます。保証会社の代わりに親族などを保証人として立ててもよい契約では、その人物の同意さえ取ればよく、審査を必要としません。
3-2. 入居審査では現在の収入・資産が重視される
大家や管理会社が行う入居審査では、収入および資産の状況が重視されます。具体的には、勤務先、現在の雇用形態、直近の年収、預貯金の状況などが審査対象です。
入居審査において、自己破産したことを申し出る義務はありません。また、開始決定した破産手続きの情報などが掲載される「官報」をチェックされたり、事故情報について調査されたりすることも基本的にはありません。
入居審査では自己破産の事実を知られる可能性はほとんどないと考えてもよいでしょう。
3-3. 信販系保証会社は利用できない可能性大
保証審査では、すでに触れたとおり「信販系保証会社」に要注意です。信販系保証会社とは、クレジットカード会社や金融機関と提携している保証会社であり、各種審査の際に加盟する個人信用情報機関(CICやJICCなど)のデータを確認します。
個人信用情報機関には、加盟する金融機関の融資記録が残っており、自己破産した事故情報も5年から10年程度にわたって残されます。いわゆるブラックリストに載った状況は、信販系保証会社が知り得ますので、賃貸借契約の審査落ちの原因になり得ます。
3-4. 独立系保証会社は利用できる見込みが大きい
一方で、借家の賃貸借契約で「独立系保証会社」と呼ばれる会社は、各種金融機関との提携がなく、個人信用情報機関のデータを確認しないのが普通です。過去の返済状況よりも現在の収入や勤務状況を重視する傾向がありますので、独立系の保証会社では自己破産歴があっても審査に通る可能性が十分にあります。
注意したいのは、家賃滞納トラブルを起こしたことがある場合です。長期間の滞納によって保証会社が代わりに支払った過去がある場合、その保証会社の審査に再び通る可能性は小さくなります。
近年では、独立系保証会社の間で全国賃貸保証業協会(LICC)による滞納情報の共有が行われているため、ほかの独立系保証会社を利用しても審査の通過が難しくなります。
4. 自己破産後の入居審査に通らない場合の対応方法

自己破産後の引っ越しで賃貸物件の審査に通らない場合でも、諦める必要はありません。物件の探し方や契約方法を意識することで、入居できる新しい家を見つけられる可能性が高まります。
次のポイントを踏まえて、信頼できそうな不動産会社の窓口で相談してみるのもよいでしょう。
- 独立系保証会社を選ぶ
- 連帯保証人をつける
- 同居人の名義で申し込む
- 公営住宅やUR賃貸を選ぶ
4-1. 独立系保証会社を選ぶ
自己破産後に賃貸住宅を探すうえでもっとも重要なのは、保証会社の厳選です。クレジットカード会社や銀行の名前がついていることが多い「信販系保証会社」は避け、独立系保証会社を選ぶようにしましょう。
なお、賃貸借契約で必要な保証会社を、大家(または管理会社)が指定するケースが多いです。気になる物件があるときは、申し込む前に会社名を確認するとよいでしょう。
4-2. 連帯保証人をつける
同意してくれる親族や知人がいるのであれば、入居申し込みの際に連帯保証人になってもらうのも良い方法です。保証会社による審査が必須となる物件でも、収入・資産の面で支払い能力が高いとみられる連帯保証人がいれば、審査上有利となる可能性があります。
もっとも、連帯保証人には大きな責任が伴うため、依頼する際には事前に十分な説明を行い、理解を得ることが大切です。とくに親族以外の人(友人や上司など)に頼むときは「家賃の支払い義務に関して、入居者と同程度の責任がある」としっかり伝えましょう。
4-3. 同居人の名義で申し込む
同居する家族や同居予定の人がいる場合、同居人を契約名義人とすることで、自己破産の影響を避けることができます。安定した収入や、信用力のあるクレジットヒストリー(個人信用情報機関に登録された返済の記録)を持つ人の名義であれば、条件の良い物件でも契約できる見込みが高くなります。
注意したいのは、住む予定のない人の名義では原則として契約できない点です。親に契約してもらって一人暮らしするようなケースでは、大家の同意を確実に得なくてはなりません。
4-4. 公営住宅やUR賃貸を選ぶ
公営住宅やUR賃貸は、保証人や保証会社を必要としない場合が多く、自己破産後でも比較的、入居しやすいです。それぞれ次のような特徴があります。
- 公営住宅
家賃が比較的低いものの、募集時期や所得制限が定められているため、事前に各自治体の情報を確認し、条件に合致するか確認する必要がある。
- UR賃貸
保証人が不要なほか、礼金や仲介手数料がかからないため初期費用を抑えられる。ただし、公営住宅よりも家賃が比較的高く、入居には収入の基準が設定されている。
5. 自己破産が賃貸借契約の連帯保証人に与える影響
賃貸住宅に住んでいる人が自己破産すると、連帯保証人に悪影響が及ぶリスクがあるため要注意です。滞納中の家賃や、原状回復費用(=退去にあたって家を元通りにするための費用)について、入居契約時に指定した連帯保証人に請求される可能性があります。
これにより、単に連帯保証人に迷惑をかけてしまうだけでなく、次の入居先を決める際に保証人を見つけられず、住居に困ることも考えられます。
5-1. 自己破産すると連帯保証人が請求を受けることがある
家賃や退去費用を滞納している状態での自己破産では、大家や保証会社による請求が連帯保証人に対して行われます。連帯保証人はこの請求を拒むことはできず、債務者本人(契約者)と同様の支払義務を負います。
自己破産で免責を認められるのは、手続きをした本人だけであり、(連帯)保証人にまで免責の効果が及ぶことはありません。免責によって回収の見込みが立たなくなった債権者(借家の大家なども含む)は、契約上の(連帯)保証人に対して請求を開始します。
このとき「連帯保証人」にあたる立場の人は、自己破産する前の債務者と同じ責任を負わなければなりません。連帯保証人も支払えない場合は、交渉により支払い計画を立てるか、保証人も債務整理する必要があります。
5-2. 連帯保証人への影響を最小限に抑える方法
賃貸借契約における連帯保証人に迷惑をかけたくないときは、できる限り家賃の滞納が始まる前に自己破産を開始することが大切です。家賃を滞納した状態で自己破産すると連帯保証人が請求を受けますが、滞納していなければ請求を受けることはありません。
なお、家賃滞納が始まるまでの間であれば、大家と話し合って契約名義を変更する、部屋を新たに借りて連帯保証人を外すといった方法があります。
6. 自己破産後の生活の不安は専門家に相談を
自己破産した後に住んでいる賃貸住宅を追い出されることは、家賃滞納などのトラブルがない限り基本的にはないものと考えられます。
注意したいのは、契約更新や入居申し込みの際の保証会社による審査です。この点に関しても、物件選びや保証人の候補者しだいで不安を解消できます。
弁護士法人プロテクトスタンスは、これまで17,000件以上の債務整理をご依頼いただき、借金問題の解決において豊富な経験を有しています(2026年2月時点)。また、単に問題を解決するだけでなく、債務整理後の生活再建まで見据えた解決策をご提案いたします。
不安を感じて踏み出せない人は、ぜひ弊事務所にご相談ください。





